読書案内 Book Review
子育てにまつわる書籍を厳選してレビュー。会員が評者となり、それぞれの視点から今取り上げたい1冊を解説します。
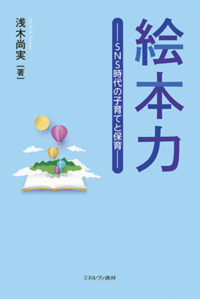
絵本力 SNS時代の子育てと保育
著者:浅木尚実 評者:小坂田 摩由
「SNS時代」と呼ばれる昨今、大人のみならず子どももスマートフォンやタブレットを常に携帯し、画面を食い入るように眺めている姿は当たり前になってきています・・・
読む
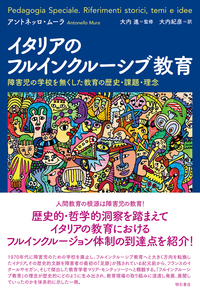
イタリアのフルインクルーシブ教育ー障害児の学校を無くした教育の歴史・課題・理念ー
著者:アントネット・ムーラ 監修:大内進 訳:大内紀彦 評者:林 恵
2022年夏の終わり、障害児を主とした特別支援教育に携わる人たちはそのニュースを聞き、自分たちの立ち位置を確認し、もしかしたら少しの苛立ちと不安を覚えたかもしれない。・・・
読む
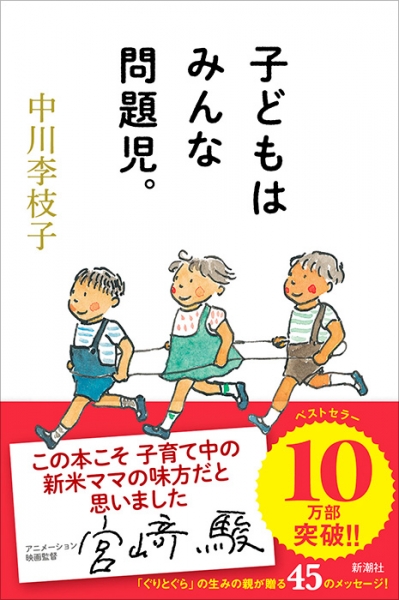
子どもはみんな問題児。
著者:中川李枝子 評者:高橋千枝
本書には「いやいやえん」や「ぐりとぐら」などの作者である中川李枝子氏の保育士(保母)時代のエピソードを通して、子ども達の素晴らしい力や子育ての楽しさが描かれています・・・
読む

エルマーのぼうけん(童話)
著者:ルース・スタイルス・ガネット 作 / わたなべしげお 訳 / ルース・クリスマン・ガネット 絵 評者:開田煌生
この本は保育園のさくら組(年長)のときに、寝る前にもり先生がいつも読んでくれました。毎日1話ずつ読んでくれました。早く寝たいなという人もいたけど、ほとんどの人は毎日楽しみにしていました。僕は、寝たくなかったので、毎日楽しみにしていた派です・・・
読む
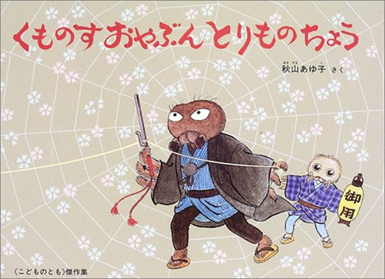
くものすおやぶん とりものちょう(絵本)
著者:秋山 あゆ子 評者:開田紗妃
私は、0歳(3ヶ月半)から保育園に入りました。6年間の保育園生活でたくさんの本に出会いました。元保育園児という立場から好きだった絵本を紹介します。4歳児クラス(ちゅうりっぷ組)の時の絵本です・・・
読む
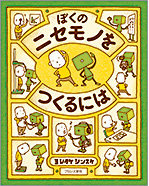
ぼくのニセモノをつくるには(絵本)
著者:ヨシタケシンスケ 評者:草山太一
もしも自分自身のことを相手に伝える必要がある場合、どのようなことをお話されるでしょうか? ストーリーは、宿題や手伝いなど、やりたくない事ばかりで気が滅入っていた主人公が、ロボットに任せることを思いつくところから始まります・・・
読む
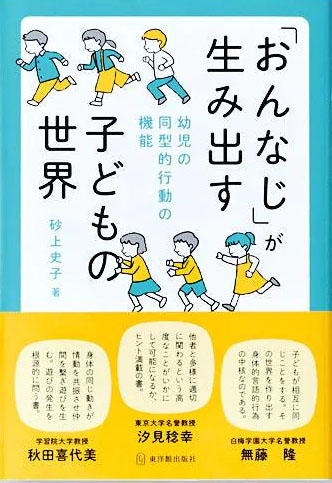
「おんなじ」が生み出す子どもの世界ー幼児の同型的行動の機能
著者:砂上史子 評者:吉永安里
本書は、幼児が他者と同じことをする同型的行動に着目し、その具体的な動き、物、発話といった媒介と特性を分析し、同型的行動が仲間関係に及ぼす影響や、仲間関係において果たす機能を明らかにしたものです・・・
読む
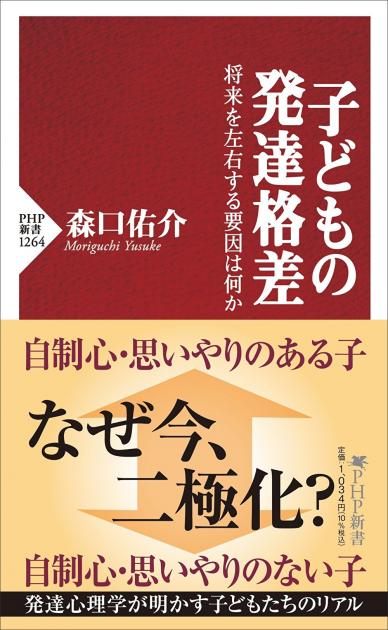
子どもの発達格差 ─ 将来を左右する要因は何か
著者:森口佑介 評者:高橋千枝
大人から目の前にある一個のマシュマロを食べることを15分我慢すればマシュマロを二個もらえると言われた時に、「今を生きる」子どもは自分をコントロールできずに目の前のマシュマロを食べてしまいます・・・
読む
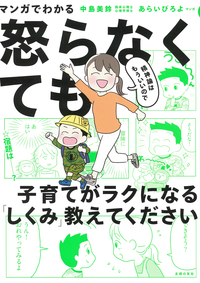
マンガでわかる 精神論はもういいので怒らなくても子育てがラクになる「しくみ」教えてください
著者:中島美玲(著)・あらいぴろよ(画) 評者:佐柳信男
この本のプロローグの章のタイトルは『「ダメなママでごめんね」はもう卒業』ですが,実はこの本,「できるママになるためのアドバイス」が書かれている訳ではありません・・・
読む
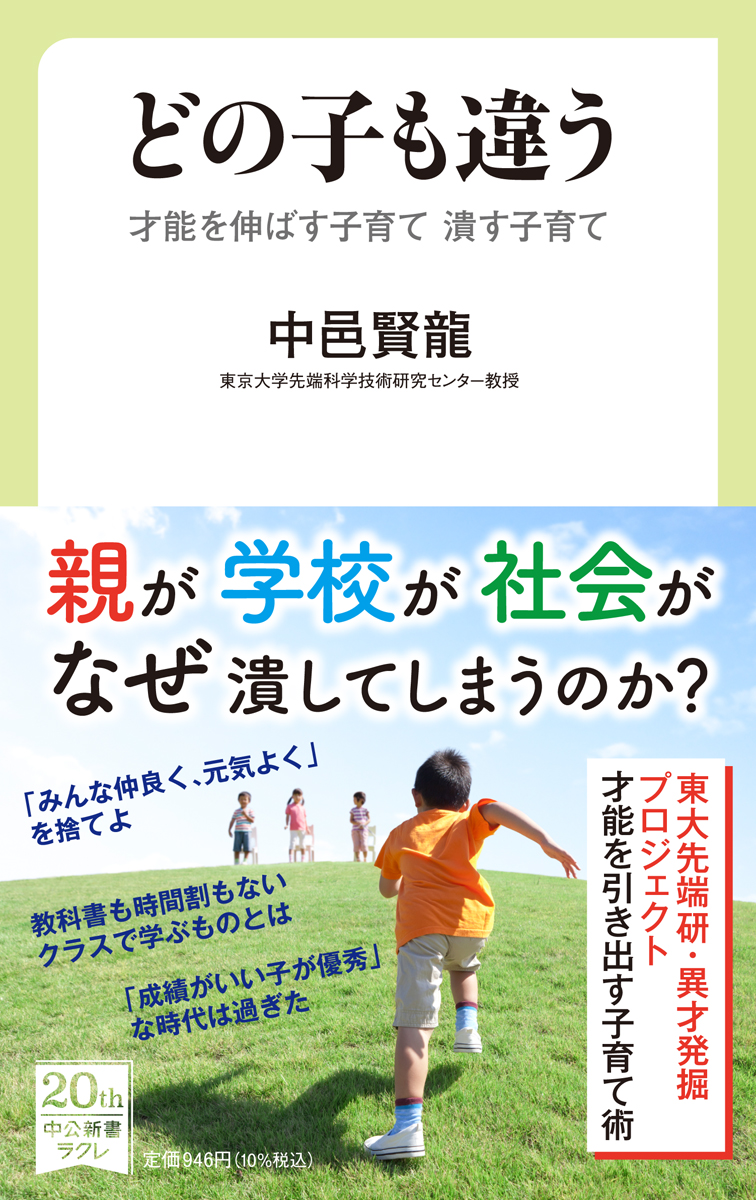
どの子も違う ─ 才能を伸ばす子育て 潰す子育て
著者:中邑賢龍 評者:荒砥悦子
自分の好きなことをしゃべってばかりいる子ども、思い通りにならないと泣き叫ぶ子ども、まったくしゃべらない子ども、ウロウロして教室に入らない子ども・・・著者はそういう子どもたちを見て、「ワクワクした」と言うのです・・・
読む
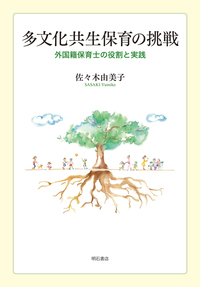
多文化共生保育の挑戦 -外国籍保育士の役割と実践─
著者:佐々木由美子 評者:新谷和代
本書での,以下のエピソードが目に留まりました。ある外国籍保育士が園庭で,日本語がまだ理解できない外国籍の男の子に向かって,「何してるの?」とその子の母国語で問いかけました。・・・
読む
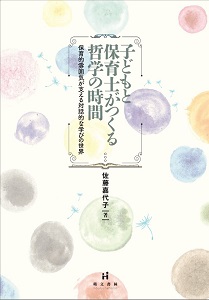
子どもと保育士がつくる哲学の時間 ─保育的雰囲気が支える対話的な学びの世界─
著者:佐藤嘉代子 評者:亀井美弥子
本書に出てくる「子どもの(ための)哲学」というアプローチは、子どもたちが対話のなかで、あるテーマについて考えや思いを分かち合うという、日本でも注目されている取り組みです。2011年にフランスのドキュメンタリー映画・・・
読む
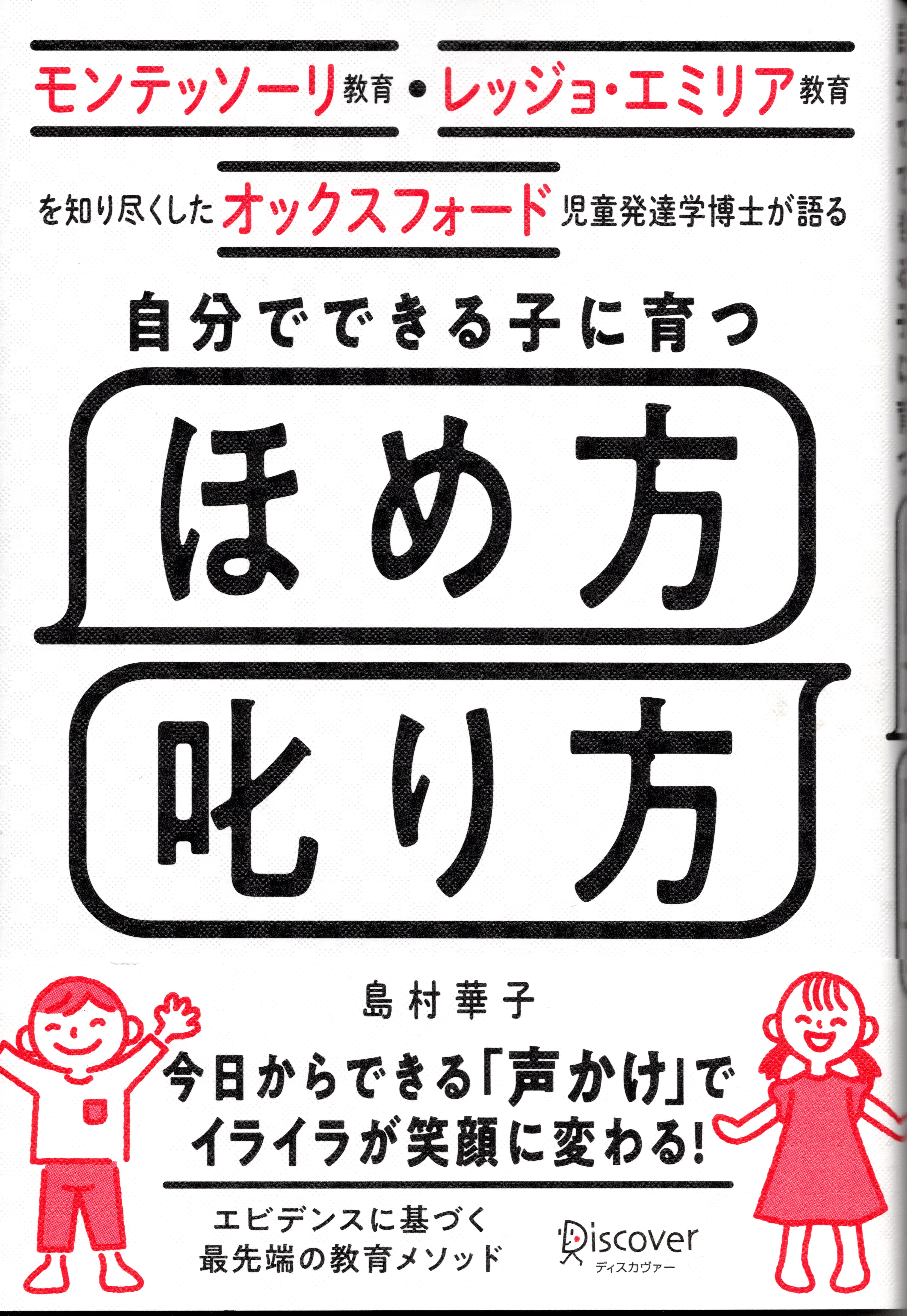
自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方
著者:島村華子 評者:濱口裕希
島村さんはこの本の冒頭で、「先の見えない時代だからこそ、自分で考え、自分で動き、未来を切り拓ける子に育ってほしい。親も子も笑顔になる『誘導しない子育て』」と記しています。モンテッソーリとレッジョ・エミリア教育研究者であり・・・
読む
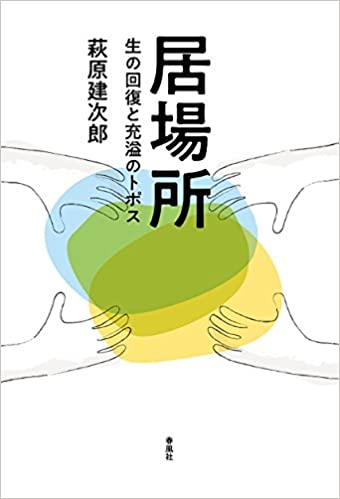
居場所 - 生の回復と充溢のトポス
著者:萩原建次郎 評者:西村美東士
萩原氏は、1997年に起こった神戸連続児童殺傷事件を起こした少年が「犯行声明文」に書いた、「透明な存在としてのボク」という「実存的な悩み」に共感する子どもや若者が存在していたことに注目する・・・
読む

子育てとケアの原理
望月雅和(編著)西村美東士・金高茂昭・安部芳絵・吉田直哉・秋山展子・森脇健介(著) 評者:佐々木 由美子
保育者・教育者には、どんなときも子どもの傍らに寄り添い受容する包容力や、子どもの可能性を信じる強さ、そしてそれを裏打ちするための適切な理解と知識が求められる。しかしながら、学習者にとって・・・
読む
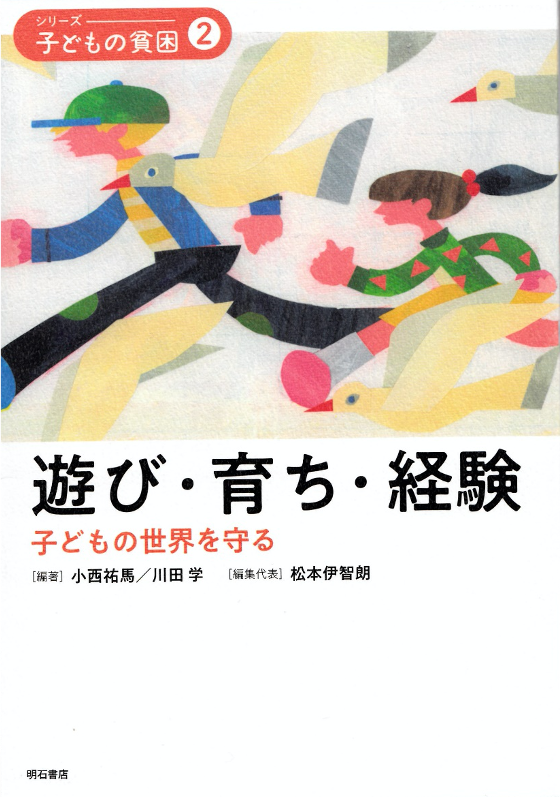
みんなが気持ちいい学童保育
長谷川佳代子 (社会福祉法人 わらしべ会理事長) 評者:矢澤圭介
[シリーズ子どもの貧困・2:「遊び・育ち・経験:子どもの世界を守る」第5章より。学童保育についてその実践の記録をまとめたもので、具体的で豊かなアイディアに充ちた実践報告となっている。・・・
読む

対人関係の発達心理学:子どもたちの世界に近づく、とらえる
著者:川上清文・髙井清子(編)岸本健・宮津寿美香・川上文人・中山博子・久保田桂子(著) 評者:繁多 進
微笑も泣きも誕生時から乳児にできる行動です。それらを使ってさかんにまわりの人々に働きかけているように見えます。そうすると、・・・
読む
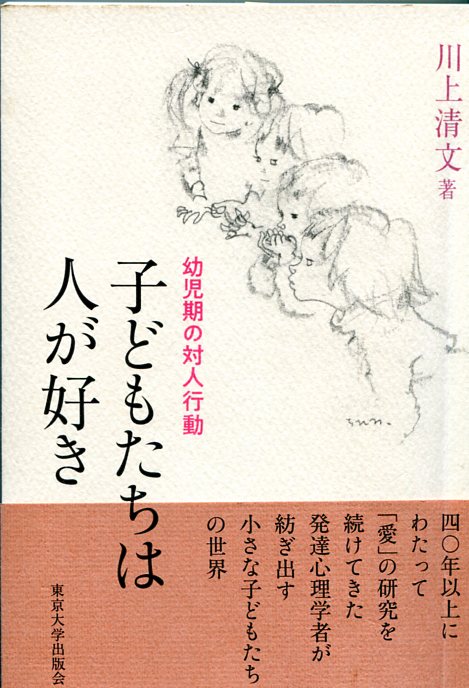
子どもたちは人が好き−幼児期の対人行動
著者:川上清文 評者:南 徹弘
ルイスの社会的ネットワーク(自己発達)理論に基づいてなされた川上清文の研究を詳細に紹介した・・・。期間にわたる乳幼児の観察から得られたデータを収集し分析することによって理論と事実の関連性に・・・
読む
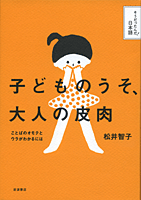
子どものうそ、大人の皮肉 ことばのオモテとウラがわかるには
著者:松井智子 評者:伴碧
子どものうそや、会話を通して相手の意図をいつからどのように理解するかなど、ことばを通じたコミュニケーションの在り方について、心理学や言語学の実際の実験結果を交えながら・・・
読む
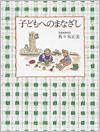
子どもへのまなざし
著者:佐々木正美 評者:小湊真衣
この本は20回にもおよぶ佐々木先生のご講演をまとめたものです。本を手に取られた方は、その厚さに驚かれるかもしれませんが、内容は先生の講演記録をもとに書かれて・・・
読む
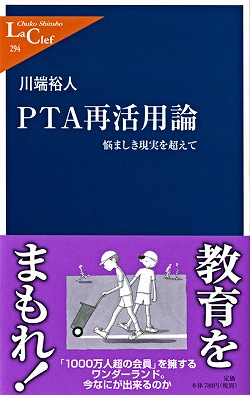
PTA再活用論:悩ましき現実を超えて
著者:川端裕人 評者:尾見康博
PTA。役員決めの際の凍り付くような,ながぁーい時間。「誰か手を挙げて」という思いむなしく,くじで外れたりじゃんけんで負けたり。それを見て・・・
読む
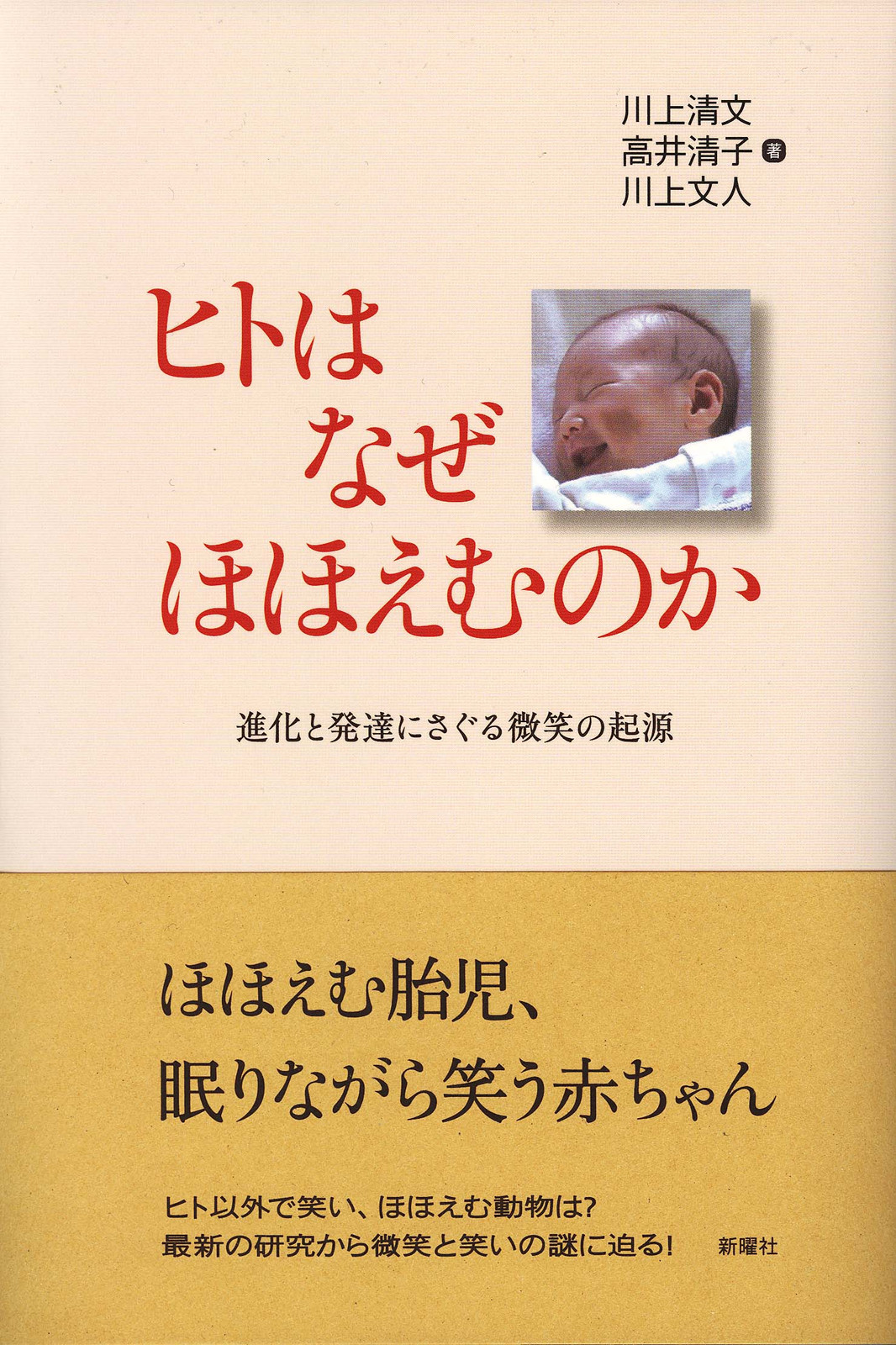
ヒトはなぜほほえむのか─進化と発達にさぐる微笑の起源
著者:川上清文/高井清子/川上文人
赤ちゃんが眠りながらほほえむのを、ご覧になったことありますか?4次元超音波により、お母さんのお腹の中にいる時から微笑していることも、わかってきました。なぜ胎児は・・・
読む
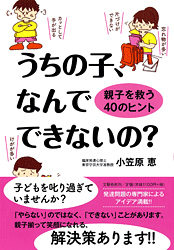
うちの子、なんでできないの?
著者:小笠原恵 評者:佐柳信男
忘れ物が多い,すぐスネる,お片付けができない,すぐに手が出てしまう…。親なら誰でも,この本で取り上げられている「気になる行動」のいくつかは自分のお子さんに当てはまるはず。しかも・・・
読む